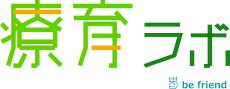療育とは関係ないように見えて、不登校の子どもは療育のお仕事をしていると高い確率で出会うと思います。
原因は様々ですが、障害や特性が原因となっている場合もあったり、診断がなくても受給者証が発行されたりしています。
今回は、そんな「不登校の子供に対して出来ること」について考えて見たいと思います。
1 不登校児に出来ること

このブログを書いている時点では、私の地域では不登校児にも受給者証が発行されており、放課後等デイサービスを利用しています。
この章では「私たちに出来ること」という視点で記事を書いていきます。
1-1 原因を探る
まず大切になってくるのは「なぜ学校に行きたくないのか」原因を知ることから始まります。
原因も分からないのに「学校は行かなきゃ行けない」では子どもの心には届きません。
そして子どもの気持ちを理解しようとする大人の姿勢が、子どもに「安心感」を与えると考えています。

対話しようとする大人の対応をみて、子どもは「受け入れて貰えた」という承認欲求をみたされるんですね。
1-2 居場所になる
なにより大切な事が「引きこもらせない」事だと考えています。
なので「最初は買い物でもなんでもいいので、必ず1日1回は外に出るようにしてください」とお話しています。
慣れてきたら「遅刻してもいいから、挨拶だけでも学校にいく」「午前中は学校にいく」「給食だけ食べに行く」など段階を踏むと良いでしょう。

毎日繰り返していると「あれ、いける!」「楽しい!」というスイッチが入る瞬間があります。
1-3 連携をとる
この項目が最も難しい部分なのですが、まずは保護者様の協力を得ましょう。
家が居心地良すぎて甘えられる環境になり「学校より家にいたい」では、引きこもってしまいます。
例えば「学校の時間はテレビ、動画などは見ない」や「学校に協力して出して貰ったプリントをする」など、学校に近い環境を作りましょう。

保護者様にも我慢や負荷がかかりますが、子どもの将来を見据えて…グッと堪えて頂きたい部分ですね。
2 まとめ

ここまで「不登校の子供に対して出来ること」ということで見てきましたが、いかがだったでしょうか?
私も公私共に、何名かの不登校児の相談に乗ってきましたが、きっかけはあり子ども自身も葛藤してはいますが、大人の優しさに甘えてる部分も垣間見えました。
いじめや人間関係など追い込まれるパターンもあるので、軽はずみなことは言えないのですが、状況をみて「ブレない大人」でいる必要はあると思っています。

ちなみに、私の関わった何名かは今は無事学校に通えています!