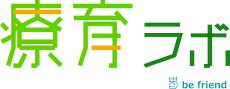今回の記事のテーマは「勝負事の力加減」ということで、賛否両論あるとは思いつつも、私自身の考えや思いを書いていければと思います。
1 勝負事の力加減

子どもと接する仕事をしていると、何かと子どもに勝負を挑まれることがあります。
そんな時「わざと負けてあげる派」と「子ども相手でも手を抜かない派」に分かれると思いますが、なぜ自分がそっちを選んでいるか意識していますか?
私は療育として「勝負事」をおこなっているからには、しっかりとした意識を持って選択をするべきだと思っています。
1-1 勝負事には手を抜かない
さすがに「向かってくる者は全力で叩き潰す」とまでは言いませんが、私はわざと負けることをしません。
そこには理由があり、療育に繋がっていますので、具体的に見ていきましょう。
①負けることも知る
これが1番初めに思い浮かぶと思いますが「負けて不安定になる」から「わざと負けてあげる」という人が多い印象です。
せっかく療育の場にいて、負けて不安定な自分を「コントロールする練習」が出来るチャンスを大人の都合で逃していることになると思います。
子どもや事業所の状況にもよりますが、子どもが不安定になるのを恐れずに敢えて「崩す」ことも必要だと考えています。
②大人の価値を高める
子どもが勝負事に負けた際に「悔しい」と思う反面「憧れ」「スゴい」という気持ちも出てくるものです。
また、これはルールゲームの仕切り役等にも言えることで、無意識のうちに仕切り役の指示を通りに動くことを続けていると、子どもは無意識に「格付け」をおこない、指示が入りやすくなります。
勝負事が終わった後に「〇〇くんくらいの時にたくさん練習したからね」「子どもの時はたくさん負けたよ」など、子どものモチベーションを高める声かけは必要になります。
③対等に扱う
私は子どもに勝負を挑まれた時は「男と男の勝負だよ!」「本気でやっていいならやろう!」等と、子どもに予め伝えておきます。
それでも挑んでくる相手には、やはり「こちらも応えなければ」と思います。
勝負をするからには相手も勝ちたいし「自分と同じ気持ち」なんだ、ということを知って欲しいと思っています。
2 まとめ

「わざと負けてあげる派」の方で「勝たせて自己肯定感を…」「勝たせて成功体験を…」と言う方がいらっしゃいますが、それは本当に「勝負に勝った事の成功体験」でしょうか?

ここまで「勝負事に手を抜かない」「勝負事は本気でやる」と言ってきましたが、私自身も調整してバレないように負けることがあるんですね。
それは勝負事を繰り返していく中で教えてきた事や課題としてる事が出来るようになった際などに、上手く負けたり、負けそうになったり、大袈裟に褒めたりしています。
私はこちらの方が成功体験に繋がり、自己肯定感が高まると思っています。


ここまで「子どもとの勝負事の力加減」を考えてきましたが、いかがだったでしょうか?
上記でも書いていますが、子どもの状況も事業所も十人十色です。「これが正しい」と主張出来ることでもないと思っています。
この記事を読んで参考になってくれれば嬉しいとは思いますが、目の前の子ども達と向き合って、良い療育をしていきましょう。